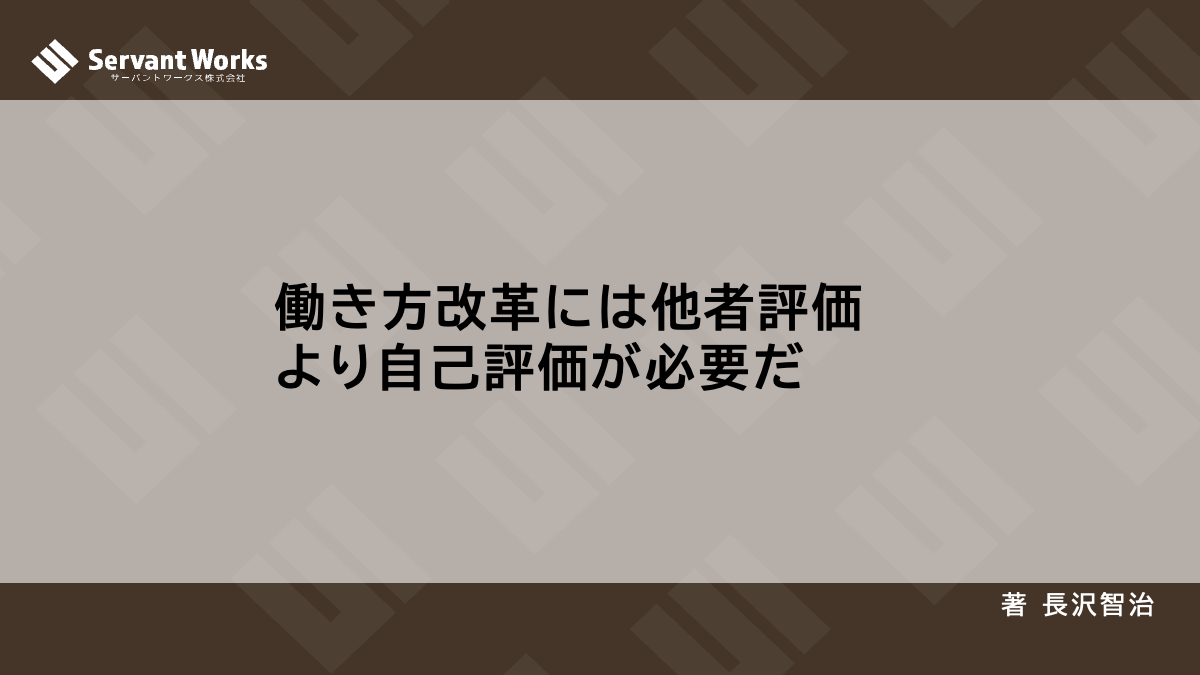自己責任でちょうどいい
以前にこのエントリーを書きました。
多くの方に共感もいただき、意見交換もできたエントリーです。
他者評価
まず、他者による評価は必要です。私の信条も
「評価は他人がするもの」
であり、評価結果については基本的に異議申し立てをしたことは一度もありません(※露骨な手柄横取り系で周りが異議申し立てしてくれたことは何度もありますがw)。
この辺りに近い見解は、こちらのエントリーでも触れた「受け手次第」がその一つの表れでもあります。
では、なぜ、働き方改革で他者評価に意義を唱えるのかというと、働き方改革自体の他者評価をあてにすべきではないということです。他者(社)と比べる、他者(社)から評価されるといったことは、必要ではありますが、十分ではありません。それよりも大切なものがあるというスタンスが大切だと考えます。
他者評価を求める改革ってなに
他者評価は客観的なものであるからとても名誉なことであり、重要視されがちです。やはり、大手メディアさんなどに「○社の働き方改革、〇〇%の生産性向上を実現!」なんて掲載されたらうれしいものです。
これにベンダーが釣られて「○社の働き方改革を支える〇〇ツール!」なんてPRするわけですから、カーニバルですwww
私は日本と世界を比較したりするのがあまり好きではないのですが、『菊と刀』(ルース・ベネディクト)での一節がとても腑に落ちました。
「日本人は、己の評価よりも他者の評価を重んじる」
(引用: ただし長沢の記憶にある言葉)
自分がどう思ったかよりも、他者がどう思ったかを重んじるのです。したがって、結果がでるまでに時間がかかります。フィードバックループが自己評価よりずっと長いのです。個人ならば、それでも他者評価で軌道修正もしていけるかもしれません。
でも組織や企業だと、他者(社)評価を待っていると内部は疲弊していきますし、フィードバックを受けいる適応生が硬直化してしまうかもしれません。そこで内発的な評価と実践のサイクルが出来上がっていればよいのですが、直線的な取り組みだと長くは続きません。
故に自己評価
自己評価は、少しずつでも行えますし、達成感も得やすいため、比較すると持続もしやすいはずです。自己評価だけで終わってしまっては自己満足で終わるかもしれません。
例えば、よくありがちなやつ:
とても革新的な企画を打ち出した。それは計画に半年を要した。予算も確保済み。あとは実行するのみ。ただし実行目処は立っていない。だが、多くの人を巻き込み、上層部も味方につけ、予算もある。当然企画者は評価された。アウトカムは未だにないに等しい。
また、自己評価だけでは、他者が納得しないこともあるでしょう。スポンサーやマネージャが満足する結果にまだ結びついていないといったことは当然に起こり得ます。でもその際に自身の自信がなければ、はねのけることも客観的なデータを示すことも困難になってしまいがちです。
以前に書いた2つのエントリーも参考にしていただければ幸いです:
以下が上記の後編です:
自己評価なく、他者評価に依存することよりも、まず自己評価することを習慣とすることは個人にとっても組織にとっても必要だと感じています。それくらいに日本は自信を失っており、自己(自社)肯定感が低いのではないかと危惧しています。
自信をつけて行きながら、世間と向き合い、そして評価という審判を受け、栄誉を勝ち取るのもおそらくはかかる時間は一緒です。できるだけ中身が残る改革にしたいものですね。
関連する記事も合わせてご覧ください:
本記事の執筆者:
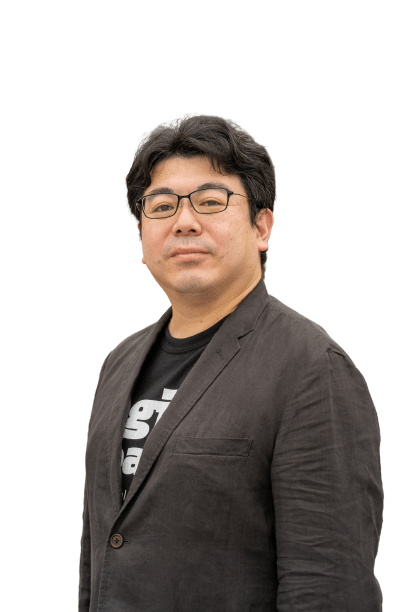
長沢 智治 – アジャイルストラテジスト
- サーバントワークス株式会社 代表取締役
- Agile Kata Pro 認定トレーナー
- DASA 認定トレーナー
認定トレーナー



認定試験合格
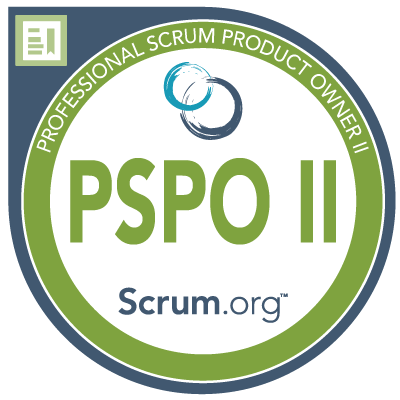
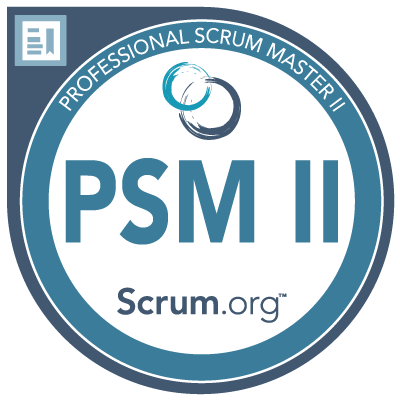
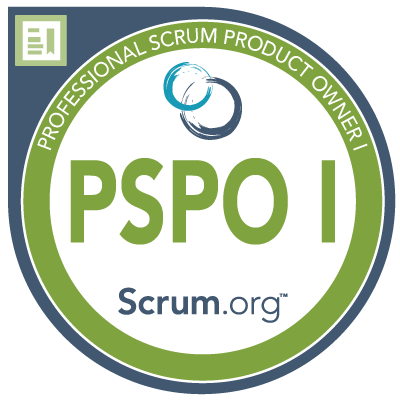
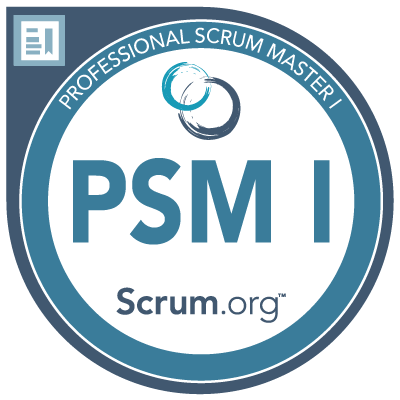


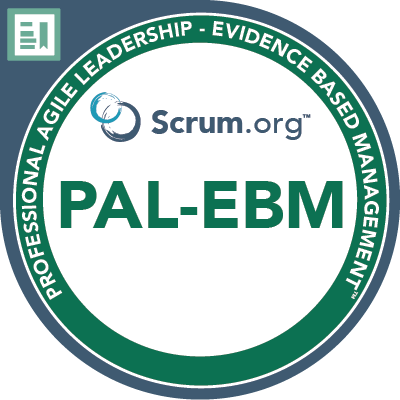
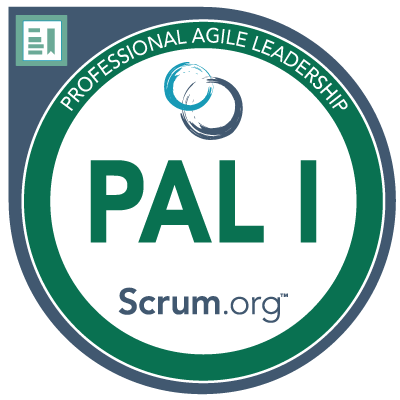

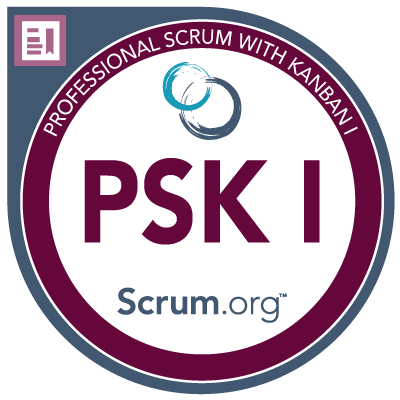
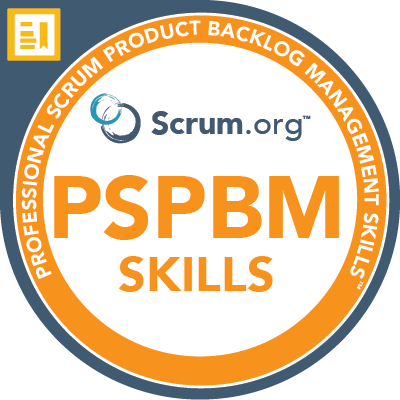
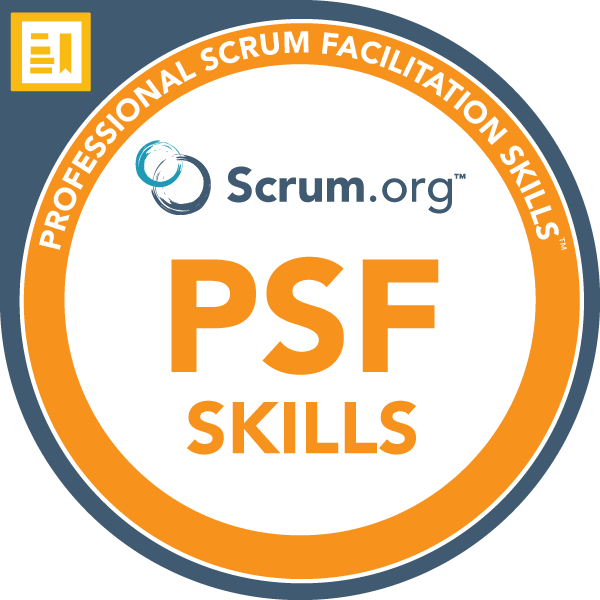
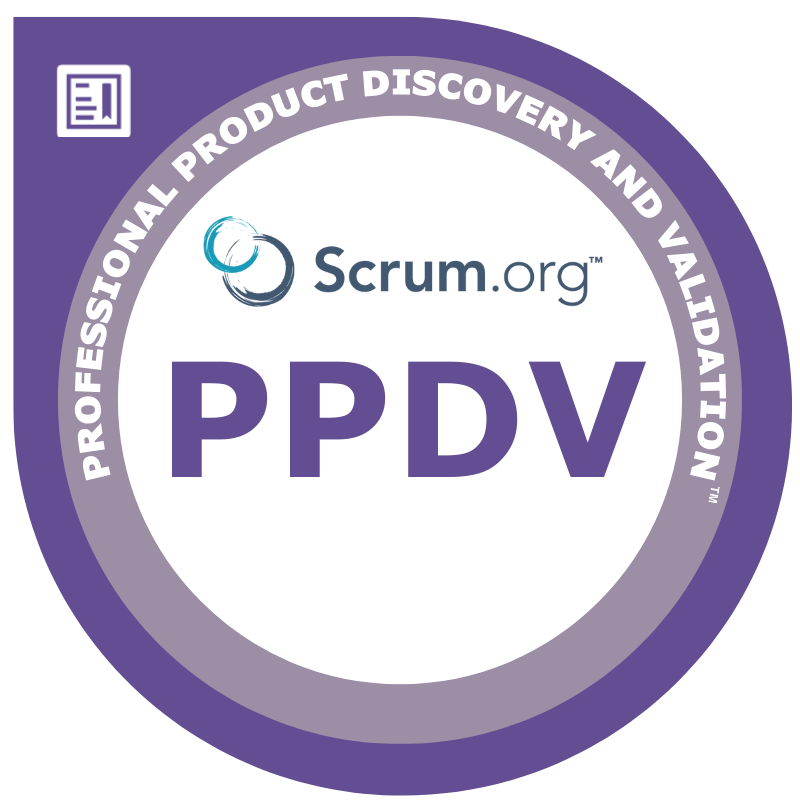
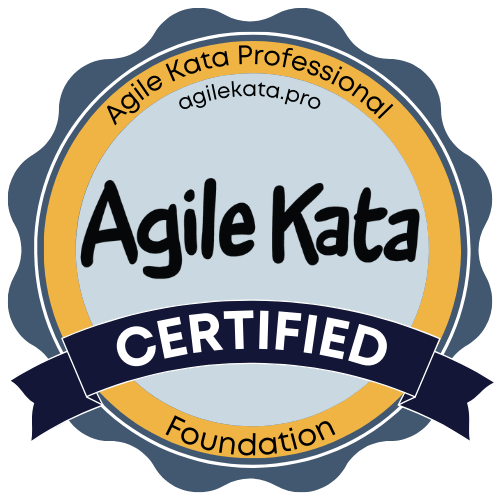



『More Effective Agile』、『Adaptive Code』、『今すぐ実践!カンバンによるアジャイルプロジェクトマネジメント』、『アジャイルソフトウェアエンジアリング』など監訳書多数。『Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテーションテクニック』著者。
Regional Scrum Gathering Tokyo 2017, DevOpsDays Tokyo 2017, Developers Summit 2013 summer 基調講演。スクー講師。