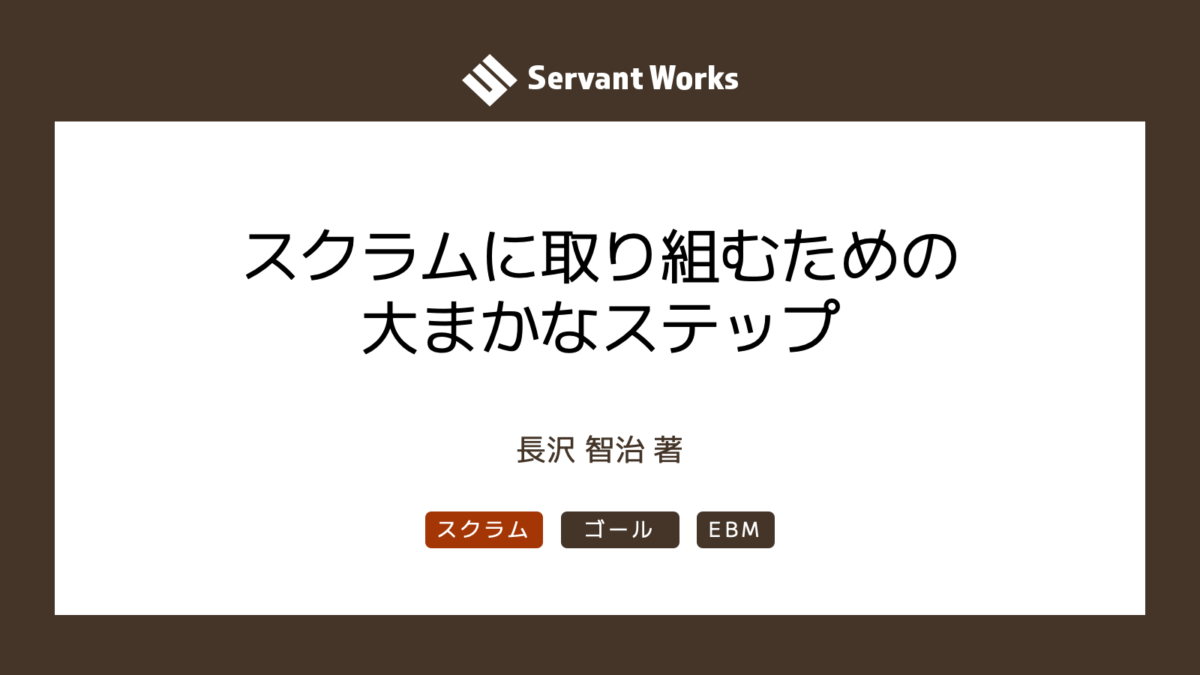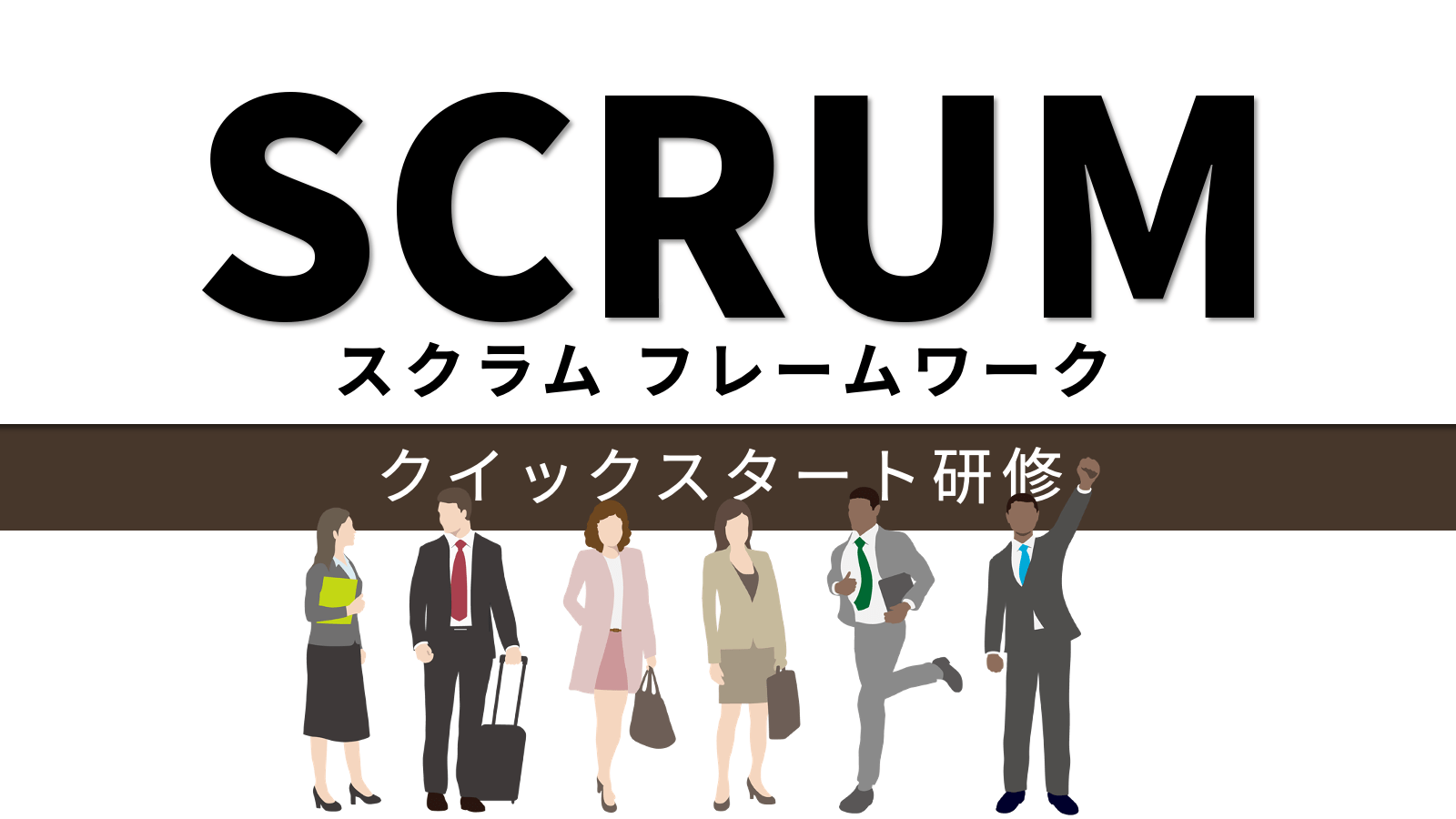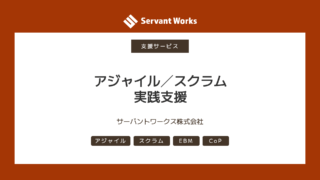はじめに
スクラムはプロダクト開発をはじめとした複雑な問題に取り組むためのフレームワークです。スクラムはまた、「スクラムガイド」として各国語版のフレームワークのガイドが提供されています。
スクラムは、スクラムのフレームワークに従うことで効果を発揮するようになっており、また意図的に不完全にしているため、そこからチームと組織の自発性、自律性、複雑な問題への取り組みに対して能動的に取り組めるようになる仕組みが備わっています。
それゆえにか、スクラムをそのまま適用せず、従来のやり方や従来の予算ありき、予測に基づくアプローチが前提でスクラムを採用してしまい、はじめかたスクラムの「カタ」を崩したり、曲解してしまう結果となることも少なくありません。
完璧とは、付け加えるべきものがなくなった時ではなく、取り去るべきものがなくなった時のことである
サン=テグジュペリ
単純であることは究極の洗練だ
レオナルド・ダ・ヴィンチ
このことをご理解いただくために、弊社のスクラム研修は、チームでの参加が前提となっており、これからスクラムを始めるチーム、スクラムを学び直ししたいチームに提供させていただいています。
スクラムの伴走支援でも、だいたいの場合、現状を把握させていただくために、以下にも紹介する事項を確認させていただいています。
スクラムを始める際の大まかなステップ
複雑な問題は、それだけでシンプルなステップや予め予測できるステップで解決するわけではありません。しかしながら、すべてが複雑な状況では取り組むことは困難なため、スクラムのフレームワークというシンプルで安定したものがあるならば、それを不安定な状況の足場にすることで、取り組みやすくすることができる可能性を高めることが重要になります。
まずは、スクラムのフレームワークを学ぶ必要があります。実践コミュニティ(CoP)などでスクラムガイドを読み合わせする、スクラムの書籍の読書会を開催する、スクラムの研修をみんなで受講するなどが手段としては挙げられます。どんなシーンで活用できるのか、どう取り組むと自分たちの組織で適用できそうかを話し合っておくとよいでしょう。
プロダクトや複雑な問題を認識します。従業員レベルでは、現場目線でスクラムが適用できそうなシーン、現場を特定し、糸口を想像するなどで大丈夫です。マネジメント、役員レベルでは、ビジネスや組織的な課題(社会課題、市場競争、DXやビジネスアジリティなど)から事実を収集することです。ここで複雑な問題と認識したものはおそらく従来のアプローチがそのまま適用できません。従って、スクラムをはじめとした今までやっていなかった取り組みをする必要性があることを認識できます。
複雑な問題とは、正解となるゴールを事前に設定することが難しいものが大半です。定まらないか、定めても状況の変化で変動してしまうからです。従って、変化する前提で方向性を定め、事実に基づいて変化させる前提のゴールを設定することになります。マネジメントや役員レベルでは、特に会社、組織としての方向性を示します。現場レベルでは、今起きている事柄から個人として、チームとしてどう向き合うべきかで比較的短期的なゴールを描きます。このとき、個人としては今後のキャリアを考慮し、複雑な問題に取り組むために各自でどのようなスキルを獲得していこうかを描いておきましょう。
方向性とゴールに基づき、このプロダクトや複雑な問題に取り組むスクラムチームを公募しましょう。もしくは、日頃のコミュニケーションに基づき適切な士気を持ったメンバーを募りましょう。目的を提示し、自発的にその問題に取り組むチームを組成することを意識しましょう。
スクラムのフレームワークに基づき、まずは実践しましょう。この際に、スクラムの学習と複雑な問題にいきなり取り組む不安を取り除くために、ステップ1.をやっておくべきだということを理解しておいてください。スクラムを実践するにあたって特別な準備は必要ありません。スプリント0などを用意することなく、スプリント1から始めましょう。最初は上手くいかないことが多いですが、それは現状が可視化されたに過ぎません。従来の取り組みでは顕在化しなかったり、後半になって露見するものが早期に現れたにすぎません。このステップでは、組織がスクラムのアプローチに適応できていないことを知ることがとても大切です。要するに組織が変化に適応できない理由が明らかになるのです。分かれば、改善・適応させることができます。
これを怠り、既存のアプローチに合わせてスクラム自体を改変してしまうと、組織の検査ができなくなります。始めから既存のアプローチに寄せすぎるということは、既存のアプローチでしかないかもしれません。すると、本来やるべき変化への対応やアジリティ、DXが損なわれないかは十分に注意する必要があるはずです。
ステップ5とは並行して進むことになりますが、複雑な問題とはわからないことの方が多い状況であることが大半です。従って、スクラムに取り組むことで、わかることを増やし、分かった事実に基づき学び、適応させていくことで、チームとプロダクトを強化していきます。ステップ5、ステップ6で重要なのが、ステップ3で示したゴールに近づけているかを検査し続けることです。これには、ゴール自体も検査し、適応させることが含まれます。具体的には、プロダクトゴールに近づけているかを検査し、やり方を適応させていきます。場合によってはプロダクトゴール自体を検査し、適応させます。
このとき、ゴール自体の検査と適応は、スクラムチームだけでは難しい、誤った道に外れてしまう恐れもあります。そこで頼りになるのはマネジメントの支援です。マネジメントはスクラムチームの設定した近位のゴールとそれを達成するためにどのように何を作るのかには口を出さない方がよいです。その代わりに、スクラムチームがこれを集中して遂行できるよう支援するのはもちろんのこと、ゴールが方向性から外れていたらそれをナビゲートすべきです。これがマネジメントによる評価なのです。
ゴールもプロダクトも、スクラムチームのやり方も、組織が変化に適応できる環境なのかも常に動向(傾向)を検査し、よりよくなるために適応させていく必要があります。これらを実践するためにも、スクラムを魔改造するのではなく、検査をしてみてください。これらのステップを経て、スクラムのフレームワーク自体に変更を加えるべきという場合は、組織としてチームとしてそれを選択してください。
スクラム概要図
このスクラム概要図では、ゴール指向を意識したものにしています。プロダクトゴールに近づいているかの検査を行いことを意識してみてください。こちらの概要図は、下記から無料ダウンロードいただけます。
よりよいスクラム体験に向けたエビデンスベースドマネジメント
上述のステップを見ていただくと、プロダクト開発を始めとした複雑な問題では、「事実」と「ゴール」が重要であり、従来のように正解がわかっていて、事前に決められる状況でないことがわかります。この場合には、マネジメント自体も変化に適応できるようにする必要があります。具体的には、マネジメントの意思決定の仕方、頻度、チームとの関わり方が変化します。このアプローチができるフレームワークとして、スクラムの考案者のひとりであるKen Schwaber氏が提唱しているのがエビデンスベースドマネジメント(EBM)のフレームワークです。スクラムと同様にEBMも経験主義に基づいています。
従って、複雑な状況下においては、スクラム以前に、EBMに取り組むことで、適切な投資と意思決定の土台を築き、その上で、スクラムにより変化に適応できる強いプロダクトとチームに繋がるともいえます。いわば、EBMが上位概念であり、マネジメント層が取り組む経験主義であり、スクラムがプロダクトとチームのための経験主義であるとも言えるかもしれません。EBMもスクラム同様に、「エビデンスベースドマネジメントガイド」が無料で提供されています(日本語を含む各国語に翻訳されています)。
まとめ
プロダクト開発を始めとした複雑な問題に取り組むには、スクラムを魔改造する前に、問題と現状を把握すること、すなわち分かっている事実と予測や憶測を区別することから始め、方向性を定め、スクラムのフレームワークをそのまま適用することで、「変化に適応する」という観点での検査と適応をしてみましょう。ただし、それだけでは難しいところがあるため、EBMにも取り組むなどで組織的に変化に適応できる環境にすることが大切になるでしょう。
本記事の執筆者:
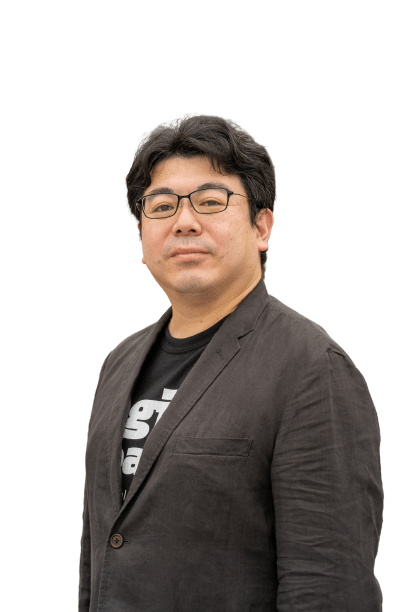
長沢 智治 – アジャイルストラテジスト
- サーバントワークス株式会社 代表取締役
- Agile Kata Pro 認定トレーナー
- DASA 認定トレーナー
認定トレーナー



認定試験合格
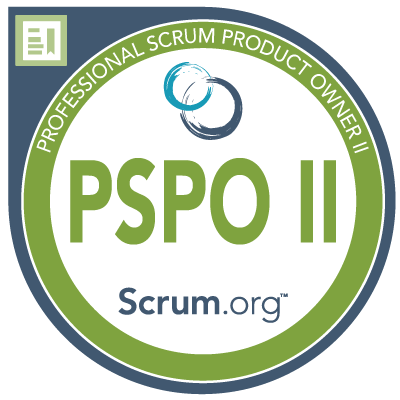
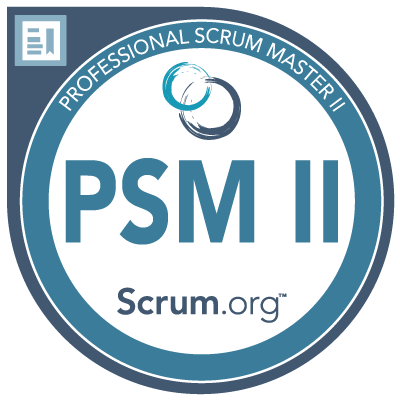
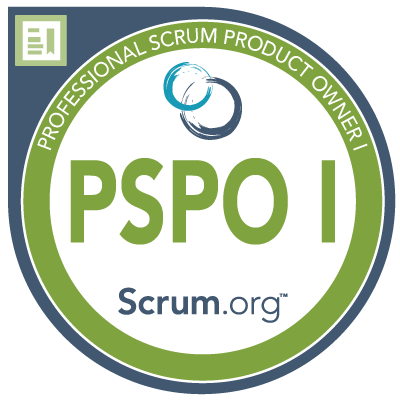
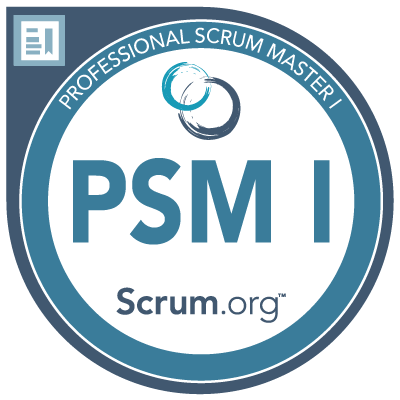


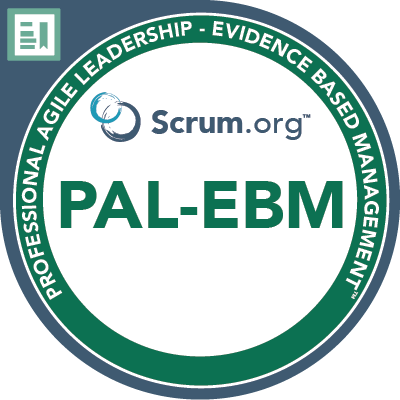
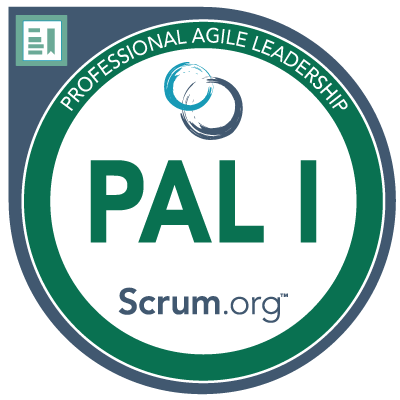

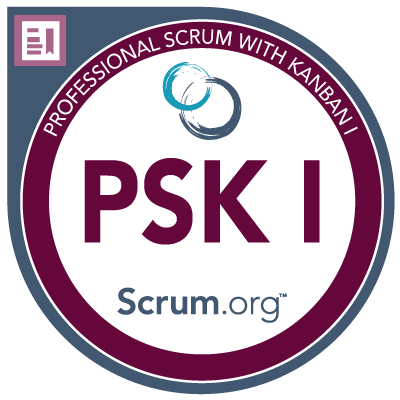
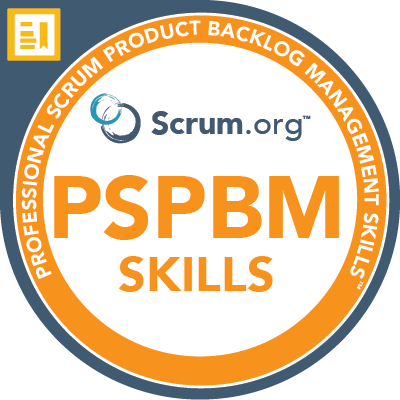
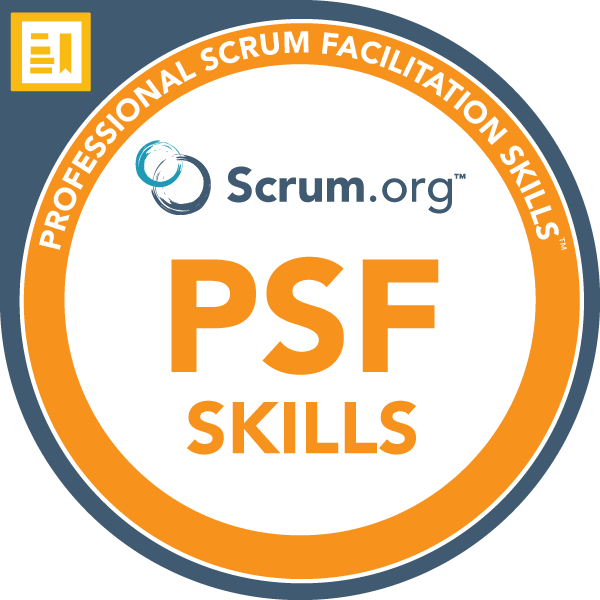
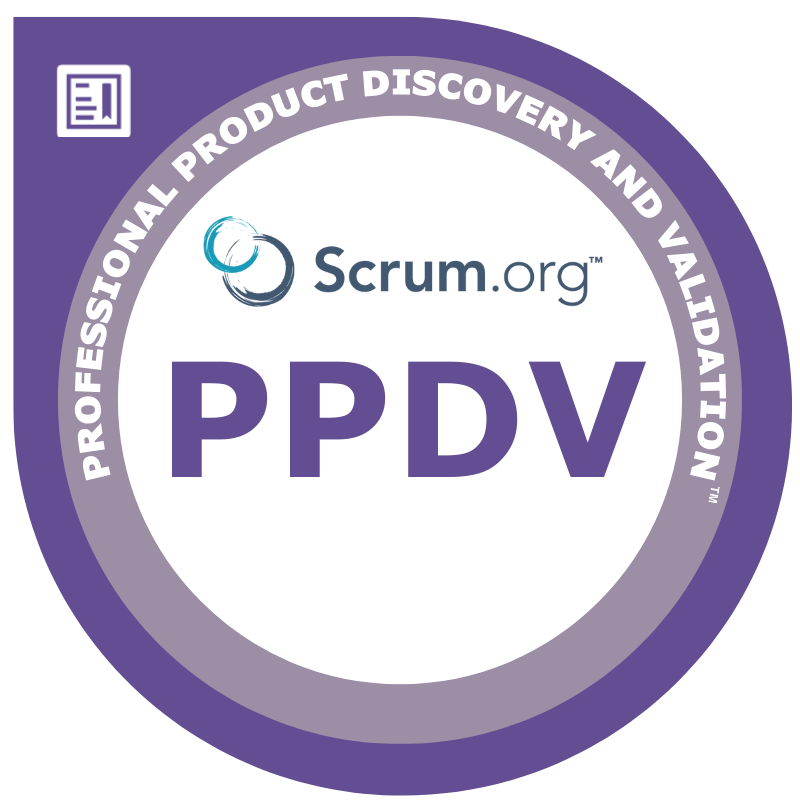
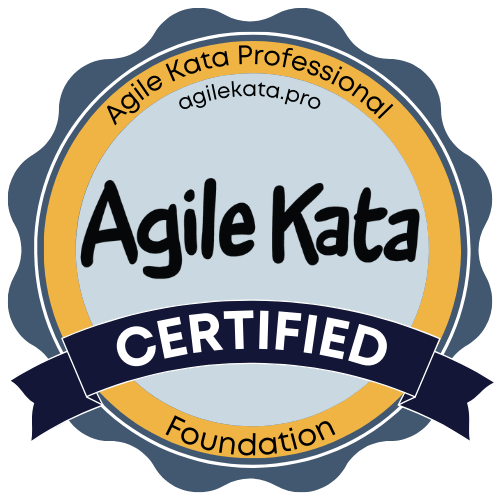



『More Effective Agile』、『Adaptive Code』、『今すぐ実践!カンバンによるアジャイルプロジェクトマネジメント』、『アジャイルソフトウェアエンジアリング』など監訳書多数。『Keynoteで魅せる「伝わる」プレゼンテーションテクニック』著者。
Regional Scrum Gathering Tokyo 2017, DevOpsDays Tokyo 2017, Developers Summit 2013 summer 基調講演。スクー講師。